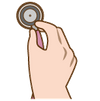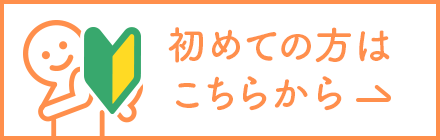肺がん検査の流れとは?
検診などで肺がんが疑われた時、まず行うのが画像検査です。状況によっては喀痰細胞診(かくたんさいぼうしん)を組み合わせることもあります。これらの検査で異常が見つかると病理検査によって肺がんが疑われる部位の細胞や組織を調べ、それががんかまたがんであればどのような種類のがんかを調べます。
肺がんと確定した後は治療方針を決めるため、再び画像検査などでがんの大きさや転移の有無を調べ、場合によってはバイオマーカー検査を用います。
それぞれの検査について、詳しく見ていきましょう。
がんの大きさや広がりを調べる画像検査
主に次の5つの画像検査によってがんの大きさや広がりを調べます。画像検査のメリットは比較的からだの負担が少ないことです。それぞれの検査に特長があり目的によって使い分けられています。
胸部X線検査
いわゆるレントゲン検査のことです。簡便なため広く普及しているので、検診などで多くの人は経験したことがあるでしょう。X線をあてて撮影すると心臓や骨は白く、肺は黒い画像になります。肺に白い影(陰影)が出た場合には、何らかの異常があるサインです。
CT検査
胸部X線検査で異常が見つかるとCT検査を行います。様々な角度からX線をあてて肺を輪切りにした画像や立体化した画像をもとに、がんの大きさや場所を調べます。
胸部X線検査より精度が高いので、淡い陰影や小さながんを映し出すことができ、いまのところ肺にがんがないか調べる画像診断のなかでもっとも有効な方法です。治療方針を決める際、リンパ節やほかの臓器に転移がないか調べる目的でも使用します。
最近は機器の性能が高まり、がん以外の小さな病変が見つかることも増えているため、がんとそれ以外の病気との鑑別がより重要になっています。
PET-CT検査
PET検査は、正常細胞より多くのブドウ糖を必要とするがんの性質を利用した検査です。放射性物質を目印としたブドウ糖を体内に注射し、その取り込みの分布を画像化してがんの大きさや場所を調べます。
PET-CT検査では、このPET検査とCT検査を同時に行います。2つの検査を組み合わせることで、より高い精度でがん細胞の有無や大きさ位置の確認ができます。肺がんの進み具合や転移の有無を調べるのにも有効です。
PET検査単独で行うこともありますが現在はPET-CT検査を用いるのが一般的です。PET検査とMRI検査が一体になったPET-MRI検査装置も登場していますが使用施設はごく少数に限られています。
MRI検査
磁気の力(磁力)を利用し、からだの内部を画像化する検査です。磁気は骨を通り過ぎるのでX線のように骨に邪魔されず臓器を映し出すことができるため、主に脳や骨への転移を調べる時に行います。放射線を利用していないので被ばくの心配もありません。ペースメーカーなど体内に金属が入っている人は、検査ができるか確認が必要です。
骨シンチグラフィ
骨への転移を調べる検査です。骨のがんの部分に放射線物質が集まることを利用した検査で、放射性物質を静脈から注射してその分布を画像化します。がんのほかに骨折の診断などに用いることもあります。
がんの“顔つき”を確かめる病理検査
同じ人間でも一人ひとり“顔つき”が違うように、一口に肺がんと言っても病理学的な特徴は様々です。適切な治療を行うためには、患者さんそれぞれのがんの“顔つき”を確かめる必要があり、そのためにがん細胞や組織を顕微鏡で調べるのが病理検査です。
細胞や組織を採取する方法はいくつかありますが、基本的にはからだに負担の少ない方法を優先します。
肺がんの病理検査には次のようなものがあり、結果が出るまでの所要日数は通常、数日から2週間ほどです。
喀痰細胞診(かくたんさいぼうしん)
痰(たん)からがんの有無を調べます。胸部X線検査では見つけることが難しい肺門部のがんが検出できます。X線検査と併用することもあります。量が少ないとがん細胞を見つけにくいため、検査には数日分の痰が必要です。
気管支鏡下検査(きかんしきょうかけんさ)・生検
胃カメラを小さくしたような、先端にカメラのついた内視鏡を鼻や口から挿入して行う検査です。内視鏡でがんが疑われる部位を確認しながら細胞や組織を採取します。苦痛を軽減させるために、スプレー式の薬で喉や気道の粘膜を麻酔(局所麻酔)して検査を行います。
経皮肺生検(けいひはいせいけん)
がんが疑われる部位まで気管支鏡が届かなかったり、気管支鏡検査で診断がつかなかったりした時に行う検査です。肋骨の間から細い針を刺し込み細胞や組織を採取します。X線、CT、超音波などで位置を確認しながら行います。気管支鏡検査よりも合併症の気胸を発生するリスクが高いため、慎重に検査を行います。
胸腔鏡下生検胸膜生検
胸を小さく切開し内視鏡を肋骨の間から胸腔内に通して、肺や胸膜、リンパ節の組織を採取して行う検査です。全身麻酔のほか最近は局所麻酔で行うこともあります。気管支鏡検査や 経皮肺生検での実施・診断ができない時などに行います。
治療方針を決めるためのバイオマーカー検査
病気の変化や治療効果の指標となる、タンパク質や遺伝子などの生体物質のことをバイオマーカーといいます。事前にこのバイオマーカーを調べることで、がんの性質を分子レベルで把握することができ、より適した治療法の選択に役立ちます。バイオマーカー検査には次のようなものがあります。
がん遺伝子検査
がん細胞には通常の細胞と異なり遺伝子やタンパク質の異常や増殖が見られることがわかっています。がん種によって検査対象となる遺伝子は異なりますが、肺がんではEGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、BRAF遺伝子、MET遺伝子、NTRK遺伝子、RET遺伝子について調べ、使用する薬を検討します。
PD-L1検査(PD-L1免疫組織化学染色検査)
がん細胞の表面にPD-L1(※注1)というタンパク質があるかどうかを調べます。PD-L1を持つがん細胞がどの程度の割合で含まれているかによって、治療薬を検討します。
※治療法については「肺がんの病期(ステージ)と手術・放射線治療・薬物療法」で紹介しています。
※注1:PD-L1は免疫細胞(T細胞)の表面にあるPD-1と鍵穴のような関係にあります。お互いがくっつき鍵穴が閉まると免疫機能にブレーキがかかり、がん細胞への攻撃が抑制されてしまいます。「免疫チェックポイント阻害剤」という薬には、そのブレーキを外し、がん細胞に対する免疫を回復させるはたらきがあります。
腫瘍マーカー検査
血液からがんの有無を調べる検査です。がんになると特異的に増える物質を「腫瘍マーカー」といい、これは血液検査で確かめられますが、がん種によって腫瘍マーカーとなる物質に違いがあります。
ただし、がんであっても腫瘍マーカーの値が高くならなかったり、がんでないのに高い値を示したりすることもあるため、あくまで抗がん剤の治療効果や経過観察の際の補助的な検査として用いられます。
【参考文献】
国立がん研究センターウェブサイト 肺がん
https://ganjoho.jp/public/cancer/lung/index.html
「国立がん研究センターの肺がんの本」(小学館クリエイティブ)
「患者さんのための肺がんガイドブック 2019年版」(金原出版)